
公的機関(文部科学省、国立特別支援教育総合研究所等)や教育委員会、大学が提供している特別支援教育に関する事例データベース・事例集をリストアップします。各リソースについて、提供元、対象領域、提供形式、主な内容、特徴、URLをまとめました。
国の公的機関によるデータベース・事例集
インクルーシブ教育システム構築支援データベース「合理的配慮」実践事例データベース(独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所/NISE)
- 提供元: 国立特別支援教育総合研究所(インクルーシブ教育システム推進センター)
- 対象領域: 合理的配慮全般(視覚障害・聴覚障害・知的障害・自閉症等、幼稚園~高等学校まで幅広く対象)
- 提供形式: ウェブデータベース(検索システム)
- 主な内容: 文科省委託事業「インクルーシブ教育システム構築モデル事業」(平成25~27年度)や「発達障害の可能性のある児童生徒の多様な特性に応じた合理的配慮研究事業」(平成30~令和2年度)で収集された約600件の実践事例を掲載。合理的配慮の具体的実践例として、子どもの障害種や特性に応じた教育上の配慮・環境整備の取り組みを事例化。
- 特徴: 充実した検索性を持ち、障害種別(視覚・聴覚・知的・自閉症など)、在籍形態(幼稚園・小学校・中学校・通常学級か特別支援学級か等)、学年、基礎的環境整備や合理的配慮の観点など多様な切り口で事例を検索可能。掲載事例数は**512件(データベースI)+78件(データベースII)**に上り(内容重複なし)、2020年度までの事業成果を収録。更新は事業完了時点までだが、2022年時点で約590事例公開との報告あり。
- URL: https://inclusive.nise.go.jp/ (※「合理的配慮 実践事例データベース」ページ)
交流及び共同学習 実践事例集(国立特別支援教育総合研究所/NISE)
- 提供元: 国立特別支援教育総合研究所(インクルーシブ教育システム推進センター)
- 対象領域: 交流及び共同学習(特別支援学校と地域の幼稚園・小中学校との交流学習事例)
- 提供形式: ウェブ上の事例集ページ(静的掲載)
- 主な内容: 心のバリアフリー学習推進会議の提言に基づき、特別支援学校の幼児児童生徒と地元の幼稚園・小中学校等の児童生徒が交流及び共同学習を行った具体的な実践事例を12件掲載。例えば、図工の授業で特別支援学校(知的障害)在籍児童が地元小学校の児童と一緒に学んだ事例や、特別支援学校(視覚障害)の幼児が地元幼稚園に週3日通って交流した事例など、多様な学習場面のケースを網羅。
- 特徴: 事例は①事前準備(授業計画作成)に注力したケース、②事前授業で相互理解を図ったケース、③実態に応じた手立て準備で円滑に参加できたケース…等、学習活動の工夫パターン別に全12事例を整理。各事例ページでは狙い・経過・合理的配慮の内容・成果等を具体的に解説。検索機能はないが一覧で閲覧可能。掲載時期は令和4年度までの研究成果として公開されたもの。
- URL: https://inclusive.nise.go.jp/交流及び共同学習実践事例集
「医療的ケア児の保育・幼児教育」に関する実践事例集(国立特別支援教育総合研究所 & 香川大学)
- 提供元: 国立特別支援教育総合研究所(研究企画部)・香川大学教育学部(共同研究)
- 対象領域: 医療的ケアが必要な乳幼児(保育所・幼稚園等での支援事例)
- 提供形式: ウェブ上の事例集ページ(静的掲載)
- 主な内容: NISE久保山研究員と香川大・松井准教授の連携研究「医療的ケア児の保育・幼児教育に関するデータベースの構築」(前川財団助成)の成果の一部として、医療的ケアを要する0~5歳児の具体的支援事例9件を掲載。例として、経管栄養(胃ろう)管理が必要な幼児の保育所生活での配慮、人工呼吸管理が必要な幼児の戸外活動における配慮、1型糖尿病でインスリンポンプ使用幼児のプール活動での配慮など、症例ごとに保育現場での具体的対応策を紹介。
- 特徴: 症例(疾患・障害別)ごとの個別支援策を簡潔にまとめ、保育現場での合理的配慮・留意点を記載。各事例はA4で2ページ程度に整理され、保護者・施設長の同意を得て写真等も掲載(一部加工)。サイト内には文科省作成の医療的ケア児受入れ支援資料等への関連リンクも掲載。研究ベースの事例集であり、更新は研究完了時(令和4年度)まで。
- URL: https://inclusive.nise.go.jp/医療的ケア児の保育・幼児教育に関する実践事例集
大学等における障害学生支援・合理的配慮事例集(日本学生支援機構調査)(独立行政法人 日本学生支援機構/JASSO)
- 提供元: 日本学生支援機構(JASSO)
- 対象領域: 高等教育における障害のある学生への支援(大学・短大・高専)
- 提供形式: PDF事例集(JASSO調査報告書、内閣府サイト等で公開)
- 主な内容: 全国の大学・短期大学・高等専門学校で障害のある学生が在籍する811校を対象に調査し、各校で実際に行われた障害学生への支援・合理的配慮の事例を収集して平成27年4月に取りまとめたもの。視覚障害、聴覚・言語障害、肢体不自由、病弱、発達障害、精神障害など障害種別ごとに具体的な配慮例(例:別室受験、時間延長、支援機器の活用、情報保障(手話・筆談)等)を掲載し、各大学の取組を紹介。
- 特徴: 教育分野(高等教育)に特化した合理的配慮事例集であり、学校種別・障害種別に整理されている。大学等における合理的配慮の基準やモデルを示すものではなく、各校の状況に応じた取組検討の参考資料として提供されている。冊子体としてまとめられており、JASSOや内閣府共生社会政策のサイトから閲覧可能。更新は調査実施時点で固定(平成27年)。
- URL: https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index_kyouiku.html (※内閣府「合理的配慮サーチ」内の紹介ページ)
高等学校における「通級による指導」実践事例集(文部科学省 初等中等教育局 特別支援教育課)
- 提供元: 文部科学省 初等中等教育局 特別支援教育課
- 対象領域: 高等学校における通級による指導(高校での特別支援教育・リソースルームの実践)
- 提供形式: PDF事例集(文科省委託研究の成果報告書)
- 主な内容: 文科省委託事業「高等学校における特別支援教育推進に関する調査研究」(平成26~28年度)の成果として、平成29年3月に文科省が全国のモデル校等での通級指導の実践事例を取りまとめたもの。高校で初めて通級による指導が制度化されるにあたり、対象生徒の決定方法、指導計画の工夫、各教科等と自立活動の連携方法、支援体制の整備などについて、複数のモデル校の実践を事例紹介。
- 特徴: 高等学校段階の実践事例集として貴重であり、各校の創意工夫が具体的に記されている。全体を通して高校への通級指導導入に関するガイド的内容も含む。事例は文章と図表で詳細に説明され、特別支援コーディネーターや担当教員向けのノウハウが満載。平成29年発行以降は改訂されていないが、文科省ウェブサイトの特別支援教育資料ページからPDFで公開されている。
- URL: https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/1400148.htm (※「高等学校における通級による指導」文科省ページ経由でPDF取得可能)
教育委員会(自治体)によるデータベース・事例集
特別支援教室 指導事例等検索サイト(東京都教育委員会)
- 提供元: 東京都教育委員会 初等中等教育局
- 対象領域: 発達障害のある児童生徒への特別支援教室での指導(公立小学校・中学校に設置された特別支援教室)
- 提供形式: ウェブデータベース(検索サイト、一般公開)
- 主な内容: 東京都が公立小中学校で展開している「特別支援教室」(在籍校で週数時間、発達障害等の児童生徒が個別指導を受ける教室)における授業の指導案や指導事例、動画コンテンツを蓄積し公開するサイト。2024年10月に更新され、現時点で指導略案44件、指導事例10件、教材例等7件が収録されている。各事例にPDFやWord形式の指導案、指導のねらいや展開、成果等の資料を添付。
- 特徴: 検索機能が充実しており、障害種(自閉症・情緒障害・学習障害・ADHD)や、育成したいスキル(例:「感情や行動のコントロール」「他者の気持ちの読み取り」など10項目)、学年(小1~中3)、資料の種類(PDF/Word等)でフィルタ可能。都内各地域の事例も含まれ、教員が自校の状況に近い事例を探せるようになっている。コンテンツは随時追加予定であり、現場のニーズに合わせ継続更新されている(最新更新:2024年10月7日)。
- URL: https://www.tokushi-case.metro.tokyo.lg.jp/special_class/ (※特別支援教室ケース検索サイト トップページ)
交流及び共同学習 事例等検索サイト(東京都教育委員会)
- 提供元: 東京都教育委員会 初等中等教育局
- 対象領域: 通常の学級と特別支援学級・特別支援学校との交流及び共同学習(インクルーシブ教育の実践)
- 提供形式: ウェブデータベース(検索サイト)
- 主な内容: 東京都が公開する上記「特別支援教室」サイトの姉妹編ともいえる検索サイトで、通常学級と特別支援学級・特別支援学校等の児童生徒が交流し共に学ぶ授業の事例を収集。令和5年度時点で指導事例4件、指導略案3件、その他4件が登録されており、教科は国語・算数/数学・理科・社会・音楽・体育・道徳・総合学習など広範囲に及ぶ。例として、小学校生活科で特別支援学級の児童と通常学級児童が共同学習した事例、中学校音楽で特別支援学校生徒が合唱に参加した事例などを掲載。
- 特徴: 教科別・学年別に検索可能で、学級種別(知的障害学級、自閉・情緒学級など)や実施主体(都立学校なのか区市町村立か)でもフィルタリング可能。事例数はまだ多くないものの、東京都や一部区市の学校から提供された事例が含まれ、インクルーシブ教育の具体策を共有する場となっている。今後もコンテンツは追加予定。東京都教育委員会の公式サイトから誰でもアクセス可能。
- URL: https://www.tokushi-case.metro.tokyo.lg.jp/kouryu/ (※交流及び共同学習ケース検索サイト)
「小学校 特別支援教室 実践事例集」(東京都教育委員会)
- 提供元: 東京都教育委員会 初等中等教育局
- 対象領域: 公立小学校の特別支援教室運営および指導の実践事例(巡回指導教員の活用等を含む運営全般)
- 提供形式: PDF事例集(分割ファイル)
- 主な内容: 東京都教委が小学校特別支援教室の円滑な運営と指導充実を目的に作成した事例集(2018年5月発行)。内容は、「教室環境整備」「巡回指導教員と在籍校教員の連携」「特別支援教室の理解促進」「指導開始・終了判定の進め方」「OJT・OFF-JTの取組」など運営・指導上のテーマごとに、実践例やQ&Aをまとめている。各章に現場の具体策(例えば教室環境の工夫事例として区切りのない開放的空間作りの紹介等)を掲載。
- 特徴: テーマごとに事例+解説形式で構成されており、単発の事例というよりベストプラクティス集に近い。全体はPDFで約60ページ程度(分割6ファイル)からなり、東京都内で先行的に取り組んだ学校の知見を反映。検索機能はないが、目次やキーワードから興味あるテーマを探しやすい構成。発行以降、内容は固定だが、上記のオンライン検索サイト開設前の蓄積として現場教員に参考とされている。
- URL: 東京都教育委員会公式サイト内(https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/ → 子供・教育 → 小中学校教育 → 特別支援教室)にPDF掲載。
合理的配慮事例集~通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある児童生徒の事例を中心に~(千葉県教育委員会)
- 提供元: 千葉県教育委員会 特別支援教育課
- 対象領域: 発達障害等のある児童生徒への合理的配慮の提供事例(主に通常学級在籍者、支援が必要なケース)
- 提供形式: PDF事例集(章ごと分割PDF)
- 主な内容: 障害者差別解消法の施行(平成28年)を受けて、千葉県教委が学校現場における合理的配慮の具体例をまとめた事例集(令和5年3月公表、最新版)。全30件の児童生徒の支援事例を収録し、第1章で法律や制度の解説、第2章で具体事例を紹介。第2章は「1.学習に関すること」(事例No.1~17)と「2.生活に関すること」(事例No.18~30)に分かれ、例えば学習面では「板書を見やすくするため黒板周りの掲示を減らした例」や「テストで別室受験・時間延長を認めた例」、生活面では「感情コントロールが苦手な生徒にクールダウンスペースを用意した例」など、多様な合理的配慮の実践を網羅。
- 特徴: 各事例は「ケースの概要(児童生徒の困難さ)」「行った配慮(具体策)」「配慮の効果」という構成で簡潔にまとめられ、教員がすぐ参考にできるハンドブック形式。発行が2023年3月と新しく、現行の制度や用語に即した内容。PDFは県教委Webサイトで公開されており、必要箇所を抜粋印刷して校内研修等に活用することも想定される。
- URL: https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shien/tokubetsushien/gouritekihairyojireishuu.html (千葉県教育委員会 特別支援教育ページ)
発達障害児等を支える指導・支援事例集(長野県教育委員会)
- 提供元: 長野県教育委員会 特別支援教育課
- 対象領域: 発達障害のある児童生徒への指導・支援全般(通常学級での支援から特別支援学級・通級指導教室での指導まで幅広く)
- 提供形式: PDF事例集(章ごと分割PDF、全4章)
- 主な内容: 長野県教委が「すべての子どもが輝き、共に学び共に育つ学校を目指して」という理念の下に作成した事例集(2016年3月発行)。内容構成は、第1章「通常の学級における発達障害児の指導・支援」(学級経営や授業づくりの工夫事例)、第2章「一部学級外での指導・支援」(リソースルーム等での個別指導事例や特別支援学級との連携活用事例)、第3章「特別支援学級での指導・支援」、第4章「ワンポイント支援」(教材・環境面の工夫集)で構成。各章内に具体エピソードが複数紹介されており、例えば通常学級編では担任が工夫してクラス全体が学びやすくなった実践や、特別支援学級編では個別のニーズに応じた指導事例を掲載。
- 特徴: 現場教師向けの実践報告+解説書の趣が強く、各事例に対して専門家の視点からのコメントやポイント整理が付されている。発行時点(2016年)での最新知見を反映しており、長野県内のモデル事例を通じて地域支援体制の構築にも触れている点が特徴。以降改訂はされていないが、全国的にも参考になる先進事例集として教育委員会サイトで公開されている。
- URL: https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/tokubetsu-shien/tokubetsushien/tokubetsushien/jireshu.html
特別支援教育 ICT活用データベース(山口県総合教育支援センター)
- 提供元: 山口県教育委員会(総合教育支援センター)
- 対象領域: 特別支援学校におけるICT活用の指導事例(タブレット端末・アプリ等の活用事例)
- 提供形式: ウェブページ上のデータベース(PDF資料の一覧)
- 主な内容: 山口県が特別支援学校にタブレット(iPad)を導入して行ったICT活用による指導法の実践研究(平成25~27年度)の成果をまとめ、各特別支援学校から提供された実践事例の一部と研修資料を公開したもの。構成は「1.個別的な学習に係る事例」「2.協働的な学習に係る事例」「3.研修用資料」「4.リンク」に分かれ、例えば個別学習では**「iPadで文章を清書しよう」(国語・肢体不自由)等の事例PDFが、協働学習では「グループで発表しよう」(国語・肢体不自由)**等の事例PDFがそれぞれ複数掲載されている。合計で20以上の具体的教材活用例を収録。
- 特徴: 一覧形式で教材名・教科・障害種別がひと目でわかるようになっており、興味あるPDFをクリックすると詳細事例を閲覧可能。事例PDFには授業のねらい、ICT機器の使い方、児童生徒の反応、成果と課題などがコンパクトにまとめられている。随時更新予定とされていたが、公開後大きな追補はないものの、当時の先進的取組として現在も閲覧可能。特別支援学校教員のICT研修資料やアプリの使い方資料も含まれ、実践と研修の両面で参考になる。
- URL: https://shien.ysn21.jp/contents/teacher/tokubetsushien/tokubetusien-ict.html
大学による実践事例集
ユニバーサルデザイン授業 実践事例集(岩手大学 教育学部附属学校)
- 提供元: 岩手大学 教育学部附属小学校・中学校・特別支援学校(※岩手大教職員が編集)
- 対象領域: ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくり(障害の有無にかかわらず全ての子にわかりやすい授業実践)
- 提供形式: PDF事例集(全45ページ)
- 主な内容: 平成25年度に岩手大学附属学校で行われたユニバーサルデザインの授業研究の成果としてまとめられた実践事例集。特別支援教育の理念に基づき、小学校・中学校の通常の学級において工夫した授業事例を中心に収録。例えば、「板書を色分けして誰もが見やすくする」「ペア学習で互いに教え合う場を設ける」「教材提示にプロジェクタを使い視覚支援を行う」等、発達障害など特性のある子も含め全員の理解度を高めた授業アイデアを具体例で紹介。
- 特徴: 各事例には授業のねらい、対象学年・教科、取り入れたUDの工夫ポイント、授業展開と成果、考察が記載されており、教科指導と特別支援の融合した内容。学校現場の教員チームが実践した検証結果であるため再現性が高く、附属学校ならではの先進的試みを共有している。岩手大学ウェブサイトでPDF公開されており、研究者・実践者双方に有用。
- URL: http://www.edu.iwate-u.ac.jp/wp-content/uploads/2016/03/UDjissenjireisyuu.pdf
特別支援教育関係 ボランティア活用事例集(文部科学省(平成21年3月)) ※参考枠
- 提供元: 文部科学省 初等中等教育局特別支援教育課(特別支援教育体制推進事業)
- 対象領域: 特別支援教育における地域人材・ボランティア活用(就学前~高等学校まで幅広く)
- 提供形式: PDF事例集
- 主な内容: 特別支援教育の体制整備を進める中で、地域の人材(大学生ボランティア等)を活用した先進事例を収集し、平成19~21年度の文科省「特別支援教育体制推進事業」成果としてまとめたもの。全国の都道府県・指定都市から寄せられた取組を、第1章で体制整備の概況解説、第2章で自治体や学校ごとの事例紹介として掲載。例として、八戸市の教育支援人材バンク活用、仙台市の学生ボランティアによる通常学級支援、山形市の大学研究室と連携した学生ボランティア派遣など、多彩なモデルが網羅されている。
- 特徴: ボランティア活用に関する先駆的事例を網羅し、組織づくりや研修方法、効果と課題を分析。各地域ごとの工夫(人材バンク制度設計、大学との連携講座開設など)は、現在のインクルーシブ教育システムにも通じるヒントとなる。冊子は文科省サイトで公開。やや年代は経ているものの、特別支援教育コーディネーターや行政担当者にも有用な資料。
- URL: https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/012.htm
注: 上記リストは代表的なものを挙げています。各リソースの最新性は2023~2024年時点で確認したものです。今後、各サイトで追加更新が行われる場合がありますので、提供元の公式ページで最新情報をご確認ください。
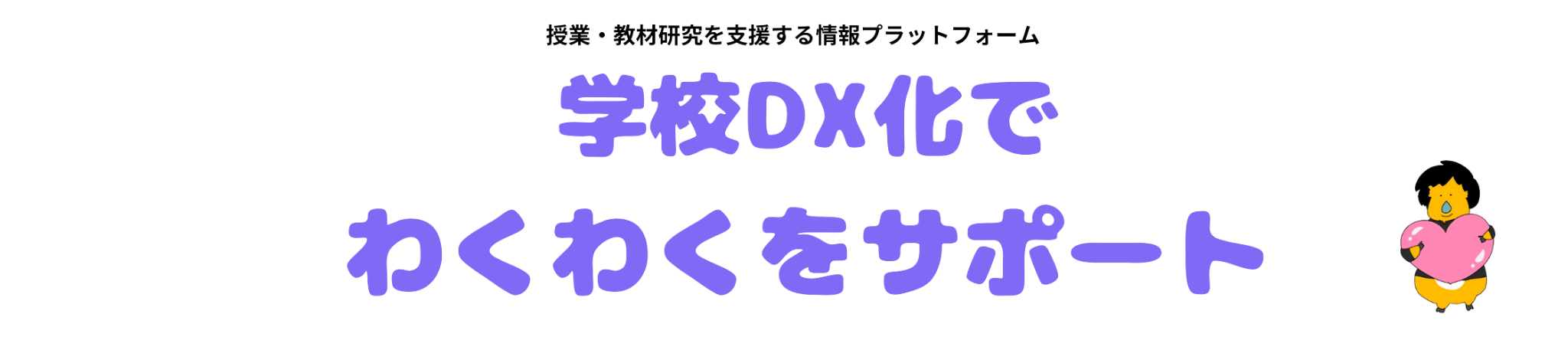

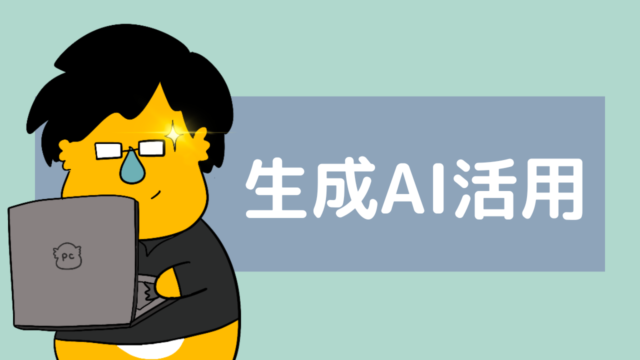
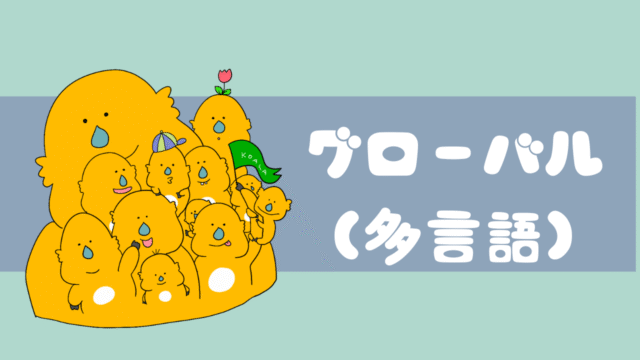
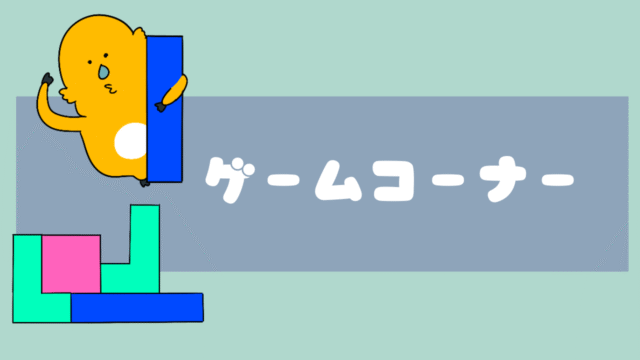
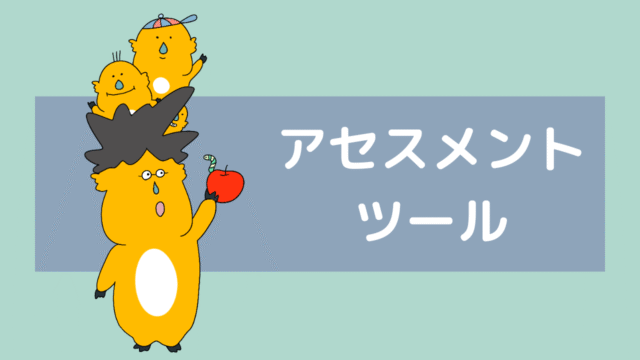

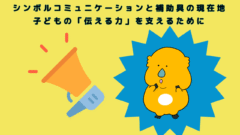
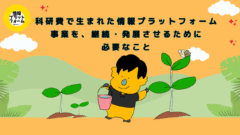
コメント